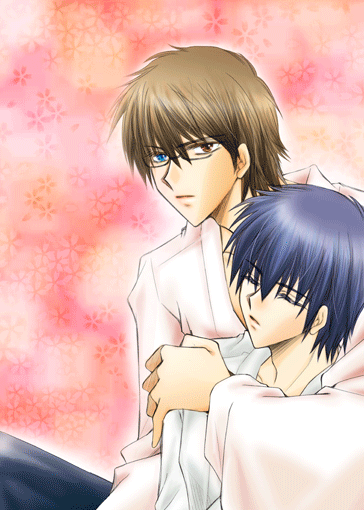
◆時代(明治辺り)モノなのでちょっと説明
◇ 介在師(かいざいし)と凪剣(なぎのつるぎ)という仕事があり、生まれつきの能力でどちらかになるか決まります。
◇ 介在師と凪剣は二人一組の対で仕事(依頼)を受けます。
◇ 力(地位)関係相関図 (長が社長なら凪剣は社員)特に覚えなくて大丈夫です。目安的なだけで。
「っあ!」
御幸の指が中を掻き回す。
その度に押さえようも無く、唇から声が零れ出た。
「…っん、…う」
脳が痺れるような刺激が、今は悦楽だと分かっている。
初めての時は、あまりの衝撃にそれが快感なのだとも分からず、自分が無くなってしまいそうなそれが、酷く怖かった。
違う。
怖いのは今でも変わらない。
「みゆ…きっ…っ」
壊れる。そう、思う。
御幸の指も唇も沢村ひとりでは知らなかった快楽を的確に掴み上げる。その融けるような快感に、なにもかもゆだねてしまいたくなる。
そんな事してはいけないのに。
がくがくと振るえる足には白濁が纏わりつきそれが自分の浅ましさを示しているようで恥ずかしかった。 太腿の内側や人には言えないような場所にはうっすらと桜色に染まった御幸の愛撫の後が残っている。
事が終わってからもしばらく残るそれは、沢村にいつでも御幸を思いださせ身体を熱く蝕んだ。
嫌だとは言えない。
抵抗なんて思いもよらない。
御幸に触れられるのは――嬉しい。
けれど御幸が優しければ優しいほど、狂おしいほど高められ口付けを受ける度に生理的なものとは違う涙が溢れ、辛くて胸が締め付けられた。
御幸は最初、沢村と組む事を嫌がっていた。
真向から睨まれ、否定された。
それでも御幸と沢村が組む事になったのは、上からの命令だからだ。
そしてそうなれば、御幸に否は無かった。
淡々と依頼を受け、大切に沢村を抱いた。
介在師と凪剣は二人一組の対になって依頼を熟す。
沢村と組むまで、御幸も何度か他の凪剣と組んでいたが、2年前から御幸は単独で行動していた。
それは本来有り得ない事であったが、御幸の能力がそれを可能とし、上もまた認めていた。
御幸の存在は、介在師、凪剣ともどもに憧れの存在として有名だった。
もちろん沢村にとっても。
「冗談じゃない!なぜ沢村なんだ!」
それが御幸の第一声だった。
沢村の方をまったく見る事もせず、上役である高島にくってかかっている。
それ事態がすでに異常だった。
介在師が上役に歯向かう事もだが、常に冷静な御幸が声を荒げるなんて今まで無かった。
沢村を見た時、顔色を変えた御幸から、歓迎の言葉が出るとは思わなかった。けれど、ここまで拒絶されるとも思っていなくて悔しさと、何より哀しくて。
滲みそうになる涙をごまかす為、慌てて下を向いた。
いつの間にか握りしめていた手が視界に入る。
歪む視界に唇を噛み締めて耐え、怒る御幸を見ていたくなくて固く目を閉じた。
力不足なのはわかっていた。
不釣り合いだという事も。
沢村が御幸の対の候補に上がってから――それも候補と言っても沢村だけだったので、すでに決定も同義だった。
陰口どころか眼前で分不相応と言い放たれ、御幸と組むのを止めろと詰られた事も一度や二度ではない。
御幸の介在師としての力は誰もが知っていたのだ。そして沢村の凪剣としての力が御幸に釣り合うものかどうかも。
御幸と組みたがっている人、御幸に憧れる人が文句を言うのも、無理はないと沢村も分かっていた。
沢村自身、なぜ自分が御幸の対に選ばれたのかまったく分からなかったからだ。
ただ、一度だけ。
御幸と組んだ事があった。
それは沢村が初めてこの里に来た時の事。
介在師は血統によるところが多いが、凪剣はそうでもない。
沢村のように、まったく普通の村里に生まれ、その能力ゆえに里に引き取られる者も、多くは無いがいる。
里に引き取られるという事は村にとって一種の栄誉でもある。
しかし同時に村にとって不気味な厄介者を追い払いたいという事情もあった。
もちろん本人も家族も望んでそのまま村里で暮らす者もいる。実際、沢村も村里で暮らしたがったし、家族も、珍しい事だが村もそれを歓迎した。
けれど異質な力を持つ者にとって、その選択は苦しく、孤独なものとなるのが常だった。
また自身の力を知らず、制御も操作も身につけられないが故に命を落とす者も少なくなかった。
そんな説明を延々と受けたが、それでも沢村は里に来るつもりはまったく無かった。なのにまるで乗り気の無い沢村をさっくり無視し、里に様子見に来る予定を高島はさっさと取り付けてしまった。
引くに引けなくなって仕方なく来た沢村が目にしたのは村里とはまるで違う空気のそこ。
力を、こんな当たり前のように受け入れられるその場に心が揺さぶられる。
けれど
「何やってんのや〜ノリ!お前もうこっから出てけや!」
「そ・そんな東さん…」
介在師と凪剣の関係はまだ知らなかった。
高島の説明で分かったのは、沢村のような力を理解し、導いてくれる仲間に出会えるという事だけ。
なのに、眼前の二人はそんな存在には思えなかった。納得いかなかったのだ。こんな、大切な仲間を踏みにじるような言動。
村里でその性格ゆえか、沢村は邪険にされる事こそ無かったが、それでも隔てなく友達になってくれた者は限られた。
変わりなく友情を分け合える友人たちは沢村にとって何よりも大切な宝だ。
村里ではあなたを理解できない――高島はそういった。
里なら――
とんだ大間違いだ。
「里、里っておエラそーに言っても中身はこんなもんかよ。」
「なんじゃあ!お前は!」
「仲間を大切にするって!分かり合える存在と信じあうってのがソレかよ!オレ絶対アンタみたいの許さねぇ!」
沢村は真向からその大男と睨みあう。その大男――東は介在師として里でも一目置かれる存在だった。この四月には里を下りて、幕府直轄になる道が決まっていたほどだ。
しかし例えそれを知っていたとしても、沢村は引かなかっただろう。
一触即発――しかし対のいない沢村に不利。 勝負以前の問題なのだから。
そんな二人の間に笑いながら入ってきたのが御幸だった。
「礼ちゃん。オレこいつの介在やって良いかな?」
ざわりと空気が動く。
「な・なんじゃぁ。御幸…っお前。そんなヤツの肩持つんかい?」
明らかに東が動揺している。
その事に疑問を感じながらも、ちりちりと何処か面白がる気配に沢村は割って入ってきた御幸に視線を映した。
「すっげぇな。お前。いきなり東さんに喧嘩売るか?」
にしし、と笑う御幸は完全に面白がっている。バカにされてるのかと沢村が口を開こうとした寸前
「お前の言ってる事は間違ってねぇよ」
ひたり、と見据えられて鼓動が跳ねる。
その瞳の中には揶揄いなど無く、強くて―優しかった。
介在師という人がいて、その人達が導いてくれるのだとは聞いていた。 けれど二人が対となって潜るなんて知らなかった。
その方法も
大体、いつも独りだったのだ。どうやって―――どうやって、あそこで一緒にいられるというのだろう。
「なんでアンタなんかと…」
東と一対一の勝負をすると思っていた沢村はワケが分からなかった。
「お前ホントに何も知らないんだなぁ」
むしろよく今まで無事にこれたな?と御幸は呆れを通り越して感心していた。もちろん笑えるという意味においてだが。しかし東の怒声が催促すると御幸は軽く返答しながら、真っ直ぐに沢村を見据えた。
「信じあう仲間を大切にするって言ったのはお前だろ?一人で勝負してどうするよ?」
言葉に詰まる沢村に御幸は続ける。
「――今まで一人だったんだろ?大丈夫だ。オレは‘ソコ’でも一緒にいるよ」
「っなんで――それを…」
村里で誰にも言えなかった、言わなかった事を指摘されて沢村は驚く。
‘ソコ’で沢村はいつも一人だった。夢を見る感覚と一番よく似ているというのだろうか。
しかしに‘ソコ’行ってしまうのは、寝ている時とは限らず、沢村にはまったく予想できない時にも引きずり込まれた。
怖かった
夢の感覚に一番似ているが、夢と違うのは毎回同じ所だと分かる事だろうか。見た目ではなく、空間そのものが‘ソコ’だと訴えてくるような感じだ。
そこに居る時は自由に動けないので、正しくは言えないが、地面に立つような感触、感覚はない。
飛んでる訳でもなく、ただそこに在る、という感じだ。
そして、その空間の更に奥深くには、沢村にはとても近づけない‘何か’があった。まるで黒い月のように見えるそこは、とても恐ろしく神聖な、それでいて禍々しい何かで凝り固まっていた。
沢村の身体はまるで鉛のように重く、どんな些細な動作でも酷く体力を消耗した。
もっとも‘戻れ’ば特に何という事もなく、 気持ち的に疲れたぐらいなのだが。
そんな中でなぜ沢村が動いたのかと言えば、時折‘ある’からだ。誰かが‘探している’といっていた物や、なぜか手に取らなければいけない、という気持ちにさせる何か、だ。
そしてそれを手にして‘戻った’時、実際に探し物が見つかったり、誰かの怪我の治りが良くなったりしたのだ。
しかしそれは同時に出来なかった時、そのまま人がずっと重い病になったり、物が壊れたりして沢村には好悪双方の噂がつきまとっていた。
幼い頃は両親や知り合いに‘ソコ’の話をしていた。
けれど誰に聞いても同じ経験をした人はなく、誰も理解してくれなかった。また次第によっては酷く不気味がられたり責められたりして、成長するにつれ沢村もそれは口にしてはいけない事なのだとわかった。
それに沢村自身も怖かったのだ。そこでは碌に動く事も出来ず、いつも沢村ただ一人しか居れなかったからだ。
もしこのまま、あの怖い場所に引きずり込まれたら。もしも閉じ込められてしまったら。
決して戻ってこれない
そんな予感がして、いつでも‘ソコ’に行くのはとても怖かった。
なのに沢村の不安を知っているのか御幸は‘ソコ’でも一緒にいる、と言ってくれたのだ。方法は分からなかったが嬉しかった。
今まで誰も言ってくれなかった――誰も知らなかったからだろうけど。けれどおそらく沢村が最も望んでいた事だ。
御幸とは会ったばかりで当然何も話していない。なのに一緒にいてくれると言う御幸を沢村は思わず真正面から見つめ返していた。沢村の驚きに気付いたのか、それとも別の何かか。
目が合うと御幸はにっ、と笑って拳を握ると軽く沢村の胸を叩いた。
「オレを信じろ。オレは――」
御幸があの時そう言ってくれたから。あの時、互いの手を取りあい鼓動を聞く。穏やかなそれに、目を閉じた沢村の唇に御幸が触れた―――その時
その時――はじめて御幸と対になった
力の開放も、異界を意識するのも。全てはじめてで。
どこまでも行ける――その世界
その時ようやく沢村は‘お前を一人にはしねぇよ’そう言った御幸の言葉の意味を知った。
村里への帰り道。沢村の頭の中にあったのは御幸だけだった。だから住み慣れた村里を出て、里に来る決意をしたのだ。
御幸と出会えたから
もう一度、御幸と――
御幸に――会いたくて
しかし、色々な手続きがあり結局沢村が里に来れたのはその時から三ヶ月が過ぎていた。
御幸はすでに里を下り、正式に鳴という凪剣と対になって以来を請け負っていると聞いた。二人は幼馴染であっただけでなく、鳴もまた凪剣として御幸に劣らず優秀な者だったらしい。
互いいに秀逸な二人はサポート的に他の者と組む事もあったらしいが、御幸が里を下りる事が決定してからは鳴と正式な対となった。
突出した二人の組に里も大きく期待していたという。詳しく分からないのは、誰も御幸と鳴の事について語ろうとしないからだ。
沢村も御幸がいなくてがっかりしたのだが、里に慣れるのに手一杯の日々で、御幸の事を詳しく知る時間などとてもつくれなかった。 ようやく御幸と再会できたのは里に来て二カ月後の事だった。
その時、御幸はすでに一人だった。
そして幕府付きでなく里に戻って上役候補としての修行を積む事になっていた。沢村を見つけ、よう、と声をかけてくれた御幸の態度は出会った時とそう変わりは無いように見えた。
けれど確実に違った。
あの時、いたずら小僧のように心底楽しそうに笑っていた御幸は無く、沢村に向けられる瞳には刹那、痛みにも似た何かが過ったのだ。
しかしその事に沢村が反応するより早く、綺麗にそれを収めた御幸は、さみしくて夜泣きしそうになったら添い寝してやるよ、などと軽口を叩いて沢村を怒らせると、満足したように笑いながら去ってしまった。
だから沢村は未だに‘鳴‘という御幸の対だった人の事を殆ど知らない。
沢村を詰った人達も「お前なんかより――」とは言ったものの、その先を続けようとはせず、鳴の名を引き合いに出す者はいなかった。
誰かがぼそりと「鳴がいたのに…っ」と小さく言葉を落としたのをかろうじて聞き取れた事で、沢村ははじめてその名を知ったのだ。
そして、今は―――
「あ…ぁっ、み、ゆ…っ」
御幸の指が沢村の弱いところばかりを攻める。すでに立つことさえままならない沢村を、御幸は片腕で抱きとめることで支え、もう一方の腕でその身体を苦しいほど高めていた。
「あ…んっ」
感じるところ全てを引きずり出されるような愛撫に身体は反射的に逃げようと足掻く。なのに御幸はそんな沢村を巧みに腕の中に戻して抵抗を奪った。
強引とも言える愛撫で沢村を高めるくせに、触れてくる指も唇もどこまでも甘やかで狂おしいほどの悦楽が沢村を侵食する。
御幸は決して沢村を傷つけない代わりに、その腕から逃してもくれなかった。
御幸の指だけでぞくぞくと背筋を這い上る快感に塗りつぶされ脳が蕩けるかと思う。
身体は一方的に高まり、開放されたくて。
決定的なソレが欲しいのに、御幸は沢村の限界が近づくとはぐらかしてしまう。
一つ一つ丹念に沢村の感じるところを開発するかのように。
堪らなくて、もどかしくて沢村は目の前の御幸に力のほとんど入らなくなった手を伸ばす。それは拒まれる事無く、御幸はずり落ちそうになる沢村を優しく抱きかかえた。
けれどやはり欲しいところには触れてくれなくて、沢村はままならない呼吸の下、必死に言葉で縋る。
「み…っゆき…」
同時に中も強請るように御幸の指を締め付けるのがわかって恥ずかしさで死にたくなる。
でも、どうしようもなく欲しかった。
指だけでなく、御幸の全部が。
沢村を抱きしめる腕を離さないでこのまま全部欲しかった。
御幸の服を握りしめ、その腕の中でむすがるように身体をすり合わせる。
御幸のくれる何もかもわからなくなるような快感に溺れてしまえれば、どんなに良いだろう。
けれど頬に触れる生地の、そのさらりとした感触に、現実を思い知らされたような気がして涙が零れた。
御幸は沢村を抱く時、衣服を乱すことすらなかった。いつもしている手袋さえ外さず、なのに沢村を際限なく高めるのだ。
沢村の肌に触れるのは最初の時と同じ。唇だけだった。
それはまるで対だから。
依頼を受けたから。
だから、仕方なく沢村を抱いているのだという御幸の気持ちの証のようで。
御幸からの口付けを、沢村はいつも固く目を閉じたまま受けていた。冷たい瞳で見据えられていたら、耐えられない。
触れてくる唇は与えられる愛撫と同じで、どこまでも甘く、優しくて。
まるで大切な宝に対する所作のようにさえ感じてしまうそれに沢村は涙を流して耐えた。
勘違いも甚だしいのだから
そして胸に過る。御幸と今まで対だった人達も、この優しい口付けを受けていたのだろうかと。
「…っあ!」
御幸の指が意地悪にそこを掠め、沢村の身体が大きく跳ねる。
「…気をそらすな」
目の前に映る御幸の瞳はいつもと同じで、静かで冷静だった。
沢村を責める色も無いし、求める色も無い―――どこまでもいつも通り。
「…ん…っう」
沢村は再び瞳を閉ざすと涙が溢れたが、拭う事もせず首を振る。御幸から気を逸らす筈ないのだと―――逸らせる筈がない。
沢村は御幸を追ってここまで来た。
いつも頭の中を占めているのは御幸だけだ。
そしてもう沢村の身体中、御幸の触れてないところなど無いだろう。特に依頼の後は、身体に残る痕がいつまでも御幸を感じさせて辛かった。
ぽろぽろと涙を零しながら首を振る沢村をどう思ったのか、御幸はそれ以上言葉を紡ぐことはせず、再び沢村を高める。もうどこまでも御幸でいっぱいで沢村は告げた。
「み…ゆっ、もうっ…」
首の後ろに手を回され、沢村はその時の為により強く瞳を瞑る。一緒に食いしばってしまう唇にふわりと御幸の匂いが近づいた瞬間。
泣きたくなるほど優しく、それが触れた。
そしてやはり沢村はその時御幸がどんな表情をしていたのか知ることはなかった。
(本文より一部抜粋)
明治辺りのイメージです。書きたかったのは
時代じゃなくてラブイチャだったんですが…
ラヴイチャにはなる!めっさこじれてますが